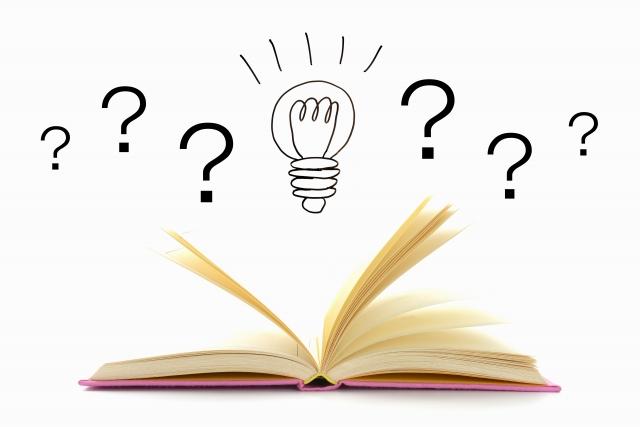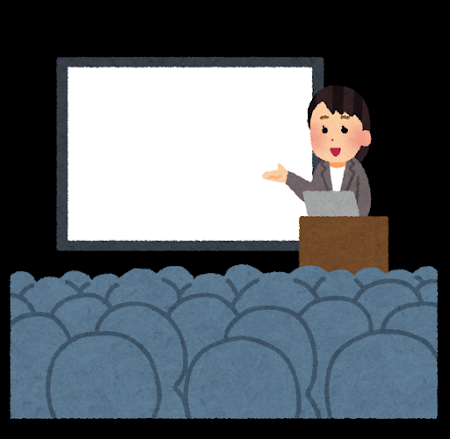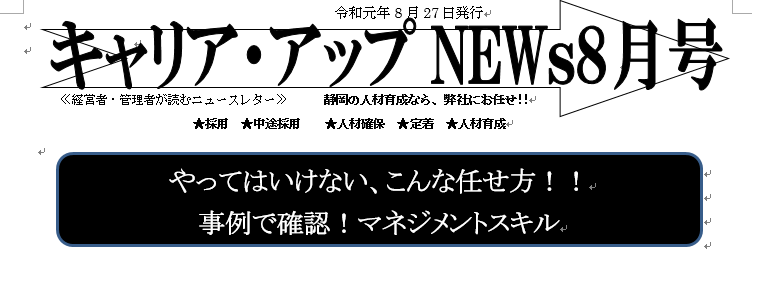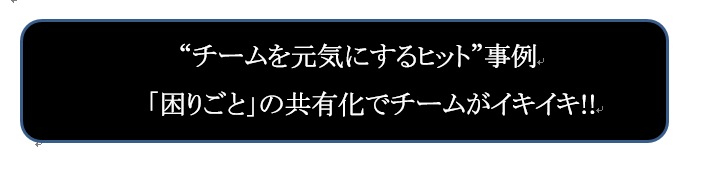8月号のニュースレターを配信しました。
今月のキャリア・アップニュースレターでは、以下の2つの話題を皆様にお伝えします。
1. 「やってはいけない、こんな任せ方!!事例で確認!マネジメントスキル」
部下への仕事の任せ方、大丈夫ですか?部下へ仕事をまかせることは、部下育成のファーストステップです。どのような任せ方が良いのか、基本に立ち返って確認してみましょう!
2. チームを元気にする ”ヒット事例” 「困りごと」の共有化でチームがイキイキ!!
組織を強くするには、社員が抱えている「困りごと」は、小さなうちに解消する事が大切です。でも、どうやって?「あれこれやってみたけど、効果的なやり方がなかなか見つからない」という企業様は必見!「あるもの」を活用し、見事に「困りごと」を解消した事例をご紹介します。
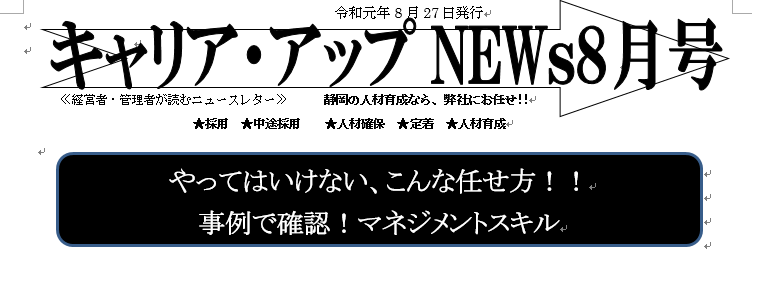
<事例>
4月から課長に昇進した花島さん。所属部署内5人の課員を取りまとめる役割になりました。今月は客先での品質問題の発生でその対応に追われる中、月初の経営委員会の資料作成もしなくてはなりません。いつもは、自分で担当資料を作るのですが、今月はなかなか時間がとれません。そこで、資料の基になるデータ作成は部下の田川さんにお願いしようと思っています。経営委員会資料の締め切りは毎月28日です。その日までにデータを基にグラフを作成し、パワーポイント形式にして総務部へメールします。
任せ方1
いちいち口頭で指示している時間はないため、メールで田川さんに資料の作成を依頼。作成法についても一通りの内容を書き、不明点は確認するようメールで依頼しました。
任せ方2
花島さんは田川さんを自席に呼び、毎月自分が作成している経営委員会資料のデータ作成を任せたい事を伝えました。なぜ田川さんにお願いしたいのか、どのようなデータを出しているか、データの出し方などを伝え、25日の昼の1時までという締め切りも伝えました。田川さんも依頼された内容は理解、納得できたようです。分からないことは何でも聞いて、と伝えました。
任せ方3
花島さんは田川さんを自席に呼び、毎月自分が作成している経営委員会資料のデータ作成を任せたい事を伝えました。このことを伝えると、田川さんの顔が曇りました。心配になったので、任せたい理由やデータの出し方などは伝えず、データ作成は花島さんが行い、グラフ化だけお願いすることにしました。


では、それぞれの対応について、見ていきましょう。
任せ方1
いくら忙しいとはいえ、すべてをメールで任せるのはNGです。どうしても時間がとれないのなら、仕事を任せたいこと、任せる仕事の背景等は直接伝え、締め切りやデータの出し方等の細かな内容はメールで送るようにします。このような場合でも、分からない事があったら遠慮なく聞いていいことを部下に必ず伝えましょう。
任せ方2
これが正解です。任せた後も中間報告をさせ、依頼した内容が正しく処理されているか、予定通り進んでいるか確認しましょう。
任せ方3
仕事を任せる際、上司にとっても不安はあるのがあたりまえです。しかし、心配だからと言って任せる内容を減らしていたり任せなかったりすれば、部下も育たず自分も苦労するだけです。この場合、まず、部下に不安点等をじっくり聞いてクリアにし、その後仕事を任せるのがベターです。任せる勇気も必要です。
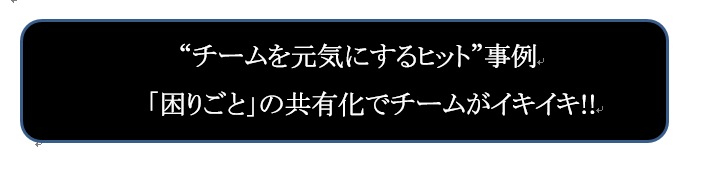
弊社は、色々な企業の人財育成・組織改善のお手伝いをさせて頂いておりますが、今回のニュースレターは、最近の私(須山)にとっての“組織改善につながるヒット”な情報をお届けしたいと思います。
こちらは、組織診断(弊社開発の「心のベクトル診断」)を組織改善につなげている、活用3年目の企業の事例です。私の立場として常に興味があることは、「元気なチーム(組織)は、一体どんなことをしているのか」ということです。そこで、今回この企業を訪問する中で、ある所属長と主任との組織改善の話がとても印象的でしたのでご紹介したいと思います。
こちらの部署では、これまで上司は部下達に気遣うつもりで「困ったことはないか」と声掛けをしてきましたが、返ってくる言葉は「ないです」であったり、また、あっても表面化されず、自分の中で何とか解消してしまうスタッフもいたようです。その結果、些細なことが積み重なり、不満の爆発や揉め事、トラブルにもつながっていったことも。また、時間を設けても、人それぞれの話す言葉の意味や解釈が違うことが多いため、上司側はサポートと共有化しているつもりが、結果的にサポートになっていなかったり。
そこで、日々の中での小さな「困りごと」を個々に聞くことも大切ですが、メンバー同士で出し合って朝礼で取り上げられるようにし、皆でその困りごとを共有し改善すること活動を始めたそうです。


◆ホワイトボードに「困りごと」を書いて共有化
最初は、「困りごと」を朝礼時に口頭で発表してもらうことが多かったようですが、口頭ですと、言葉は消えてしまうので、本当の意味での共有化にならなかったようです。人それぞれ話す言葉の意味や解釈が違うことが多いため、本来の意味からずれたりして、共有化しているつもりが、結果的に共有化できていなかったこともあったようでした。

そこで、あるメンバーからの提案で、「困りごと」を事前に、ホワイトボードに書いてもらうことを始めました。まず、「困りごと」に対して、書いた本人に発表してもらい、そこで議論すると同時に、出た結果も確実にホワイトボードに板書することをしたそうです。
すると・・・言葉や意味のズレがなくなり、仲間同士の「困りごと」の解決と共有化ができ、その後チームの足並みが揃う大きなきっかけにもつながったということでした。
また、今回の朝礼では何件挙げられたのかが視覚でわかるため、発表するスタッフも1件にかけられる時間を予測し、事前に自分の頭を整理し効率的に「困りごとの共有化」ができるようになったそうです。特に、彼らが言うには、ホワイトボード活用と解決策の板書は、「全員共通認識で仕事に取り組める」大きなきっかけにつながったようです。


◆小さな困りごとの解決と共有化がスタッフの前向きさへ
毎日のわだかまりや疑問を解消して日々の業務につなげているため、以前よりチームでのぶつかり合いや葛藤が減り、とても前向きに仕事ができているということです。ただ、ここで重要なことは、出された「困りごと」に対して、上司は批判や否定的な対応をしないことがベースにはあるということです。
以上のことより、小さな不安や疑問を日々解消できる環境があること、また、その対策を全員で共有すること、それが、チームがイキイキ前進する一つのコツであることを実感しました。
須山由佳子